
「御社のホームページ、最後に更新したのはいつですか?」企業サイトの多くは公開後に放置され、情報が古くなり、セキュリティリスクも高まっています。実はホームページは公開してからが本番。適切な管理なしでは、せっかくの投資が無駄になってしまうことも。本記事では、ホームページの価値を維持・向上させるための管理方法を徹底解説。自社対応と外部委託の比較、具体的な管理業務、費用相場まで、ホームページ運用のすべてがわかります。企業の顔となるホームページを最大限に活用するための知識を、今すぐ手に入れましょう。
目次
ホームページはリリース後の管理が重要
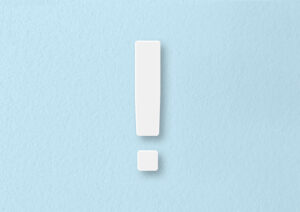
ホームページを公開した後、「これで終わり」と考えてしまう企業は少なくありません。しかし、実際にはホームページのリリース後こそが本当のスタートなのです。公開したままのホームページは、時間の経過とともに情報が古くなり、検索エンジンからの評価も下がっていきます。
現代のビジネス環境では、ホームページは企業の「顔」であり、24時間365日稼働している営業マンのような存在です。そのため、常に最新の情報を反映し、訪問者に価値を提供し続ける必要があります。
また、WEB技術やデザイントレンドの変化に対応するためにも、定期的なメンテナンスは欠かせません。セキュリティ面においても、放置されたホームページはハッキングなどの攻撃対象になりやすく、情報漏洩などの深刻な問題を引き起こす可能性があります。
つまり、ホームページの価値を維持・向上させるためには、公開後の継続的な管理が非常に重要なのです。計画的な更新と適切な管理によって、ビジネスの成長に貢献するホームページであり続けることができます。
ホームページ管理の具体的な方法は?
ホームページ管理は大きく分けて、コンテンツ管理、技術的管理、運用管理の3つの側面があります。それぞれの観点から適切な管理を行うことで、ホームページの価値を最大化することができます。持続的にWEBサイトの運営をしていくために、必要不可欠な「ホームページの保守」に関する記事も合わせてご覧ください。
ホームページの保守とは何をすべき?作業内容やかかる費用などをまとめて解説!
ホームページの内容に関する業務
コンテンツは訪問者が直接目にする部分であり、ホームページの価値を左右する最も重要な要素です。魅力的で有益なコンテンツを継続的に提供することが、成功するホームページの秘訣と言えるでしょう。
コンテンツを定期的に追加する
ホームページに新しいコンテンツを定期的に追加することは、訪問者の興味を維持し、検索エンジンからの評価を高める上で非常に効果的です。ブログ記事や新製品情報、お知らせなど、様々な形でコンテンツを追加することができます。
定期的な更新によって、「このサイトは活発に運営されている」という印象を与えることができ、ユーザーの信頼感も高まります。また、Google などの検索エンジンは、定期的に更新されているWEBサイトを高く評価する傾向があるため、検索順位の向上にも繋がります。
コンテンツ追加の頻度は業種やターゲットによって異なりますが、最低でも月に1回は更新することをおすすめします。更新計画を立てて、計画的にコンテンツを追加していくことが、継続的な運営の秘訣です。ユーザーの疑問や悩みに答えるコンテンツを提供することで、ホームページの価値は大きく向上します。
コンテンツの質をブラッシュアップする
既存のコンテンツを定期的に見直し、品質を向上させることも重要な管理業務です。古くなった情報の更新、文章の読みやすさの改善、画像の最適化など、様々な角度からコンテンツをブラッシュアップすることができます。
特に、よくアクセスされるページや重要なランディングページは、定期的に内容を確認し、最新の情報に更新することが大切です。例えば、「よくある質問」ページは、新たな質問が寄せられるたびに内容を充実させることで、ユーザーの疑問解消に役立ちます。
また、ユーザーからのフィードバックやアクセス解析データを活用して、コンテンツの改善点を見つけることも効果的です。bounce rate(直帰率)が高いページがあれば、内容を見直し、ユーザーにとって価値のある情報を提供できているか再検討しましょう。質の高いコンテンツは、訪問者の満足度を高め、結果的にコンバージョン率の向上につながります。
トレンドにあったデザインに適宜変更する
WEBデザインのトレンドは年々変化しています。5年前のデザインを現在も使用していると、時代遅れの印象を与え、企業イメージにも影響を及ぼす可能性があります。定期的にデザインをリフレッシュすることで、現代的で洗練された印象を維持することができます。
最近のトレンドとしては、モバイルファーストデザイン、ミニマリズム、大きな写真や動画の活用、マイクロインタラクションなどが挙げられます。これらを取り入れることで、ユーザーエクスペリエンスを向上させることができます。
ただし、デザイン変更の際は、ブランドの一貫性を保ちながら、ユーザビリティを損なわないよう注意が必要です。大幅なリニューアルは2〜3年に一度程度、部分的な改善は必要に応じて随時行うのが理想的です。特にユーザーの行動パターンが変化したり、新しいデバイスが普及したりした場合は、それに合わせたデザイン調整が必要になることもあります。
デザインに関して最新版のトレンドを掲載した記事も合わせてご覧くさい。
【最新版】WEBデザインのトレンド20選!厳選したモダンなデザインを一挙公開!
ドメイン/サーバー管理に関する業務

ホームページの安定した運用のためには、ドメインやサーバーといった技術的な部分の管理も欠かせません。これらは表面的には目立ちませんが、サイトの安全性や継続性を支える重要な要素です。
ドメインの登録期限/支払いの確認
ドメイン名は通常1年〜10年の期間で登録し、期限が来ると更新する必要があります。この更新を忘れてしまうと、ドメインが失効し、ホームページにアクセスできなくなる可能性があります。最悪の場合、他者に取得されてしまうこともあるため、管理は慎重に行う必要があります。
ドメイン登録会社(レジストラ)からは、通常、更新期限の数ヶ月前から通知メールが送られてきますが、これを見落とすことも少なくありません。そのため、ドメインの更新日をカレンダーに登録しておくなど、自社でも管理する仕組みを作っておくことが重要です。
また、複数のドメインを所有している場合は、それぞれの更新時期を一覧にしておくと管理がしやすくなります。ドメイン管理は比較的シンプルな業務ですが、忘れた場合の影響が大きいため、担当者を明確にし、確実に対応することが求められます。自動更新設定が可能なレジストラを選ぶのも一つの方法です。
SSL証明書の内容を確認
SSLは、ホームページとユーザー間の通信を暗号化する技術で、「https://」で始まるURLはSSLが導入されていることを示しています。現在ではGoogleなどの検索エンジンがSSL導入サイトを優遇する傾向にあり、また利用者のセキュリティ意識も高まっているため、SSL証明書の導入は必須と言えるでしょう。
SSL証明書にも有効期限があり、通常は1年〜3年程度です。期限切れになると、ブラウザ上に「安全ではない」などの警告が表示され、訪問者に不安を与えることになります。SSL証明書の更新も、ドメインと同様にカレンダーなどで管理しておくことが重要です。
また、SSL証明書にはいくつか種類があり、単純な暗号化だけでなく、組織の実在証明が含まれる高度な証明書もあります。特にECサイトなど、個人情報や決済情報を扱うサイトでは、信頼性の高い証明書を選択することが望ましいでしょう。自社のビジネスに適したSSL証明書を選び、適切に管理することがセキュリティ対策の基本となります。
サーバーのセキュリティー対策
ホームページのセキュリティ対策を怠ると、不正アクセスやマルウェア感染などのリスクが高まります。特に近年は、企業サイトを標的としたサイバー攻撃が増加しており、適切な対策が求められています。
基本的なセキュリティ対策としては、サーバーやCMSの定期的なアップデート、強固なパスワード設定、不要なプラグインの削除などが挙げられます。特にWordPressなどのCMSを利用している場合は、脆弱性が発見されるたびに更新プログラムがリリースされるため、常に最新版を維持することが重要です。
また、ファイアウォールの設定やアクセス制限、定期的なセキュリティスキャンの実施も効果的です。万が一、セキュリティ侵害が発生した場合に備えて、インシデント対応プランを事前に策定しておくことも大切です。セキュリティ対策は専門知識が必要な分野ですので、不安がある場合は専門業者に相談することをおすすめします。
データのバックアップ
ホームページのデータは、サーバーの故障、操作ミス、サイバー攻撃など、様々な理由で失われる可能性があります。そのため、定期的なバックアップの取得は、ホームページ管理において非常に重要な業務の一つです。
バックアップは、ホームページのファイル(HTMLやCSS、画像など)とデータベース(記事内容やユーザー情報など)の両方を対象に行う必要があります。バックアップの頻度は、サイトの更新頻度によって異なりますが、一般的には週に1回程度が目安となります。ECサイトなど、日々データが変化するサイトの場合は、より頻繁なバックアップが望ましいでしょう。
また、バックアップデータは、メインサーバーとは別の場所に保存することが重要です。クラウドストレージや外付けハードディスクなど、複数の場所に分散して保存しておくと、より安全です。復旧手順をマニュアル化しておくことも、緊急時にスムーズに対応するためのポイントとなります。
その他の業務

ホームページの効果を最大化し、ビジネス目標を達成するためには、コンテンツやサーバー管理以外にも様々な業務が必要です。これらの業務はマーケティング的な側面も持ち、サイトの価値向上に大きく貢献します。
お問い合わせフォームの対応
問い合わせフォームは、潜在顧客との重要な接点です。フォームからの問い合わせに迅速かつ適切に対応することは、顧客満足度を高め、ビジネスチャンスを逃さないために非常に重要です。
まず、問い合わせが届いた際の社内フローを明確にしておきましょう。誰が確認し、どのように対応するのか、返信の目標時間なども設定しておくと良いでしょう。一般的には、24時間以内の返信が望ましいとされています。
また、問い合わせ内容の傾向を分析し、よくある質問についてはFAQページを充実させることも効果的です。これにより、同じ質問への対応時間を削減でき、ユーザーにとっても即座に情報を得られるメリットがあります。
さらに、問い合わせフォーム自体の使いやすさも定期的に確認しましょう。必要以上の入力項目があると、ユーザーが離脱してしまう原因になります。シンプルで使いやすいフォームデザインを心がけることが大切です。
定期的なアクセス解析
アクセス解析は、ホームページの改善に不可欠なデータを提供してくれます。Google Analyticsなどのツールを使用して、訪問者数、滞在時間、流入経路、離脱ページなどの情報を定期的に確認しましょう。
特に注目すべき指標としては、コンバージョン率(目標達成率)、直帰率(1ページだけ見て離脱する割合)、セッション時間(滞在時間)などがあります。これらの数値が良好であれば、ユーザーにとって価値のあるサイトと言えます。
また、アクセス解析データからユーザーの行動パターンを把握し、導線の改善やコンテンツの強化に活かすことも重要です。例えば、特定のページでの離脱率が高い場合は、そのページのコンテンツやデザインを見直す必要があるかもしれません。
定期的なレポート作成と分析を行うことで、ホームページの効果を測定し、継続的な改善につなげることができます。データに基づいた戦略的な運用が、ホームページの成功への近道と言えるでしょう。
SEO対策
検索エンジン最適化(SEO)は、Googleなどの検索エンジンからの自然流入を増やすための重要な施策です。適切なSEO対策を行うことで、ターゲットとするキーワードでの検索結果上位表示を目指します。
SEO対策の基本としては、キーワード選定、メタタグの最適化、質の高いコンテンツ作成、内部リンク構造の改善などがあります。特に近年は、ユーザー体験を重視したコンテンツが評価される傾向にあり、単なるキーワード詰め込みではなく、実用的で価値のある情報提供が求められています。
また、モバイルフレンドリーなデザイン、ページ表示速度の改善、構造化データの実装なども、現代のSEOでは重要な要素となっています。検索エンジンのアルゴリズムは常に変化しているため、最新のSEOトレンドを把握し、適宜対策を更新することが大切です。
SEO対策は即効性のあるものではなく、継続的な取り組みが必要です。しかし、長期的に見れば、広告費をかけずに安定した集客が見込める効果的な方法と言えるでしょう。
ホームページへの集客
SEO以外にも、ホームページへの集客方法は様々あります。リスティング広告、SNS広告、メールマーケティング、コンテンツマーケティングなど、目的やターゲットに合わせた施策を選択することが重要です。
効果的な集客のためには、まずターゲットユーザーを明確にし、そのユーザーがどのようなチャネルを利用しているかを把握することが必要です。例えば、若年層向けのサービスであればInstagramやTikTokなどのSNSを活用した集客が効果的かもしれません。
また、オフラインとオンラインの連携も重要です。展示会やセミナーなどのイベントで配布する資料にQRコードを掲載したり、店舗内にホームページの案内を設置したりするなど、様々なタッチポイントからの誘導を考えましょう。
集客施策の効果は必ず測定し、費用対効果の高い方法に予算を集中させることがポイントです。定期的に集客経路を分析し、戦略を見直すことで、より効率的な集客が可能になります。
ホームページの管理を自社で行うべき?委託したほうがいい?

ホームページ管理の方法は、自社で行う方法と外部に委託する方法があります。どちらを選択すべきかは、自社のリソースや専門知識の有無、ホームページの規模や重要度などによって異なります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、最適な選択をしましょう。
自社で行っても問題ないケース
自社でホームページ管理を行うことで、コスト削減や即時対応が可能になるなどのメリットがあります。以下のような条件が揃っていれば、自社管理も十分に検討する価値があるでしょう。
ホームページ管理に関する専門知識を持った人材がいる
社内にWEBデザイン、HTML/CSS、SEO、サーバー管理などの知識を持つ人材がいる場合は、自社でのホームページ管理が可能です。専門知識を持った人材がいれば、更新作業やトラブル対応を迅速に行うことができ、外部委託するよりもコスト面で有利になることが多いでしょう。
特に、コンテンツ管理システム(CMS)を導入しているサイトでは、基本的な更新作業は専門知識がなくても対応できる場合があります。WordPressなどの一般的なCMSは、直感的な操作が可能で、ITリテラシーがあれば記事投稿や画像追加などの基本操作は習得しやすいです。
ただし、デザイン変更やシステム改修、セキュリティ対策などの専門的な作業については、それに対応できる知識とスキルが必要です。自社管理を検討する際は、社内人材のスキルレベルとホームページの要求レベルのバランスを考慮することが重要です。適切な人材育成や継続的な学習環境の提供も、自社管理成功の鍵となります。
管理方法がマニュアル化されている
ホームページ管理の作業がマニュアル化されており、明確な手順に沿って誰でも対応できる状態になっていれば、自社での管理がスムーズに行えます。特に、担当者が変わっても混乱なく引き継げるような体制が整っていることが重要です。
効果的なマニュアルには、定期的な更新作業の手順、トラブル発生時の対応フロー、バックアップの取得方法、セキュリティチェックリストなどが含まれるべきです。スクリーンショットや動画を活用して視覚的に分かりやすく説明することも有効です。
また、管理業務のスケジュール化も重要なポイントです。例えば、「毎週月曜日にコンテンツ更新」「毎月第一金曜日にバックアップと脆弱性チェック」など、定期的なタスクを明確にすることで、抜け漏れを防ぐことができます。
マニュアルは一度作成して終わりではなく、ホームページのリニューアルやシステム変更があった際には、そのつど更新することが大切です。適切にメンテナンスされたマニュアルは、自社でのホームページ管理を成功させるための重要なツールとなります。
委託した方がいい場合
ホームページ管理を外部に委託することで、専門的なノウハウを活用し、高品質な運用が期待できます。以下のようなケースでは、外部委託が適している可能性が高いでしょう。
どのような作業をしたらいいのかわからない
ホームページ管理に関する知識や経験がなく、何をどのように対応すべきか分からない場合は、専門業者への委託を検討すべきです。WEBサイトの技術や最新トレンドは日々進化しており、素人が独学で対応するには限界があります。
特に、サーバー管理やセキュリティ対策は専門知識が必要な分野で、不適切な対応はサイトダウンやセキュリティ侵害などの深刻な問題を引き起こす可能性があります。専門業者は最新の技術動向や脅威に関する情報を常に更新しており、適切な対応が期待できます。
また、SEOやWEBマーケティングの分野も、効果的な施策を実施するには専門的な知識が不可欠です。競合サイト分析やキーワード戦略、コンテンツ最適化など、プロフェッショナルのノウハウを活用することで、より高い成果が期待できるでしょう。
専門業者への委託は費用がかかりますが、効率的かつ効果的なホームページ運用を実現することで、長期的には投資対効果の高い選択となる可能性があります。
本業のビジネスに専念したい
多くの企業にとって、ホームページ管理は本業ではありません。限られた時間と人材を、自社の強みを活かせる本業に集中させることで、ビジネス全体の成長を図ることができます。
ホームページ管理を自社で行うと、更新作業やトラブル対応、セキュリティ管理など、様々な業務に時間を取られることになります。特に小規模な企業では、一人のスタッフが複数の役割を担当することが多く、ホームページ管理が負担になる場合もあるでしょう。
外部委託することで、これらの業務から解放され、本来注力すべきビジネス活動に集中することができます。また、定期的な報告を通じてホームページの状況を把握しつつ、細かな作業は専門家に任せるという効率的な体制を構築することが可能です。
「選択と集中」の観点から、自社の強みを最大限に発揮できる分野に経営資源を集中させ、専門性が求められる分野は外部の専門家に任せるという判断は、ビジネス戦略として合理的と言えるでしょう。
高品質なSEO対策を実施したい
効果的なSEO対策を実施するには、検索エンジンのアルゴリズムに関する深い理解と経験が必要です。専門業者に委託することで、最新のSEOトレンドに基づいた施策を実施することができます。
SEO対策は、キーワード選定、コンテンツ最適化、内部リンク構造の改善、技術的SEOの実装など、多岐にわたる作業が必要です。また、Googleのアルゴリズムは年間数百回も更新されており、常に最新の動向をキャッチアップする必要があります。
専門業者は複数のクライアントサイトを運用することで豊富な経験を持ち、何が効果的で何が効果的でないかを実績に基づいて判断できます。また、専門的なツールを活用した競合分析やパフォーマンス測定も可能です。
高品質なSEO対策は、長期的に安定した自然検索流入をもたらし、広告費の削減にもつながります。特に検索流入がビジネスの重要な集客チャネルである場合は、専門業者への委託を検討する価値があるでしょう。
ホームページ管理を自社で行う場合と委託する場合の費用を比較!

ホームページ管理を自社で行うか外部委託するかを決める際、費用面の比較は重要なポイントです。それぞれのケースにおける費用構造を理解し、自社のニーズに最適な選択をしましょう。
ホームページ管理を自社で行う場合の費用
自社でホームページ管理を行う場合、主な費用はスタッフの人件費、必要なツールの導入費、トレーニング費用などが挙げられます。
まず、人件費については、ホームページ管理に割く時間によって計算する必要があります。例えば、週に5時間の作業が必要で、担当者の時給が2,000円とすると、月間で約4万円の人件費が発生することになります。小規模なサイトであれば少ない工数で済みますが、ECサイトや頻繁に更新が必要なサイトでは、かなりの時間が必要になることもあります。
次に、ツール費用としては、CMSのプラグイン、セキュリティ対策ツール、バックアップツール、アクセス解析ツールなどが必要になります。無料のツールも多いですが、より高度な機能を利用する場合は有料版を検討する必要があるでしょう。こうしたツール費用は、月額数千円から数万円程度と見積もることができます。
また、サーバー費用やドメイン費用も自社管理の場合は自社で負担することになります。サーバーは月額数千円から、ドメインは年間数千円程度が一般的です。
さらに、担当者のスキルアップのための研修費用も考慮すべきでしょう。WEB技術は日々進化しているため、定期的な学習が必要です。書籍購入やオンライン講座の受講などで、年間数万円程度の費用が発生する可能性があります。
これらを総合すると、小規模なサイトの自社管理では月額5〜10万円程度、中規模サイトでは月額10〜20万円程度の費用がかかると想定できます。ただし、既存スタッフの業務の一部としてホームページ管理を行う場合は、追加の人件費は発生しない可能性もあります。
ホームページ管理を委託する場合の費用
ホームページ管理を外部の専門業者に委託する場合、費用体系は大きく分けて定額制(月額固定)と従量制(作業量に応じた課金)の2種類があります。
定額制の場合、月額1万円〜10万円程度が一般的な相場です。サイト規模や更新頻度、サポート内容によって料金は変動します。小規模なコーポレートサイトであれば月額1〜3万円程度、中規模サイトやECサイトなどでは月額5〜10万円程度が目安となるでしょう。
定額制プランに含まれるサービス内容としては、以下のようなものが一般的です。
- 定期的なコンテンツ更新(月に数回程度)
- セキュリティ対策とアップデート
- バックアップの取得と管理
- 軽微な修正・改善
- 簡易的なアクセス解析レポート
一方、従量制の場合は、作業内容や難易度によって料金が設定されます。例えば、文章のみの更新であれば1ページあたり3,000円〜、画像を含む更新であれば5,000円〜、デザイン変更を伴う場合は1万円〜といった具合です。大規模なリニューアルやシステム改修になると、数十万円から数百万円の費用が発生することもあります。
また、SEO対策やWEBマーケティングを含む包括的なホームページ運用を委託する場合は、月額10万円〜30万円程度の費用が一般的です。これには、キーワード戦略の立案、コンテンツマーケティング、アクセス解析と改善提案などが含まれます。
委託費用は一見すると自社運営よりも高く感じられるかもしれませんが、専門的なノウハウや最新技術の活用、トラブル対応などを含めた総合的な価値を考慮する必要があります。また、自社スタッフの工数を他の業務に充てられることによる間接的なメリットも大きいでしょう。
ホームページ管理の管理は制作会社に委託するのがおすすめ!
ホームページ管理を効率的かつ効果的に行うには、ホームページ制作会社への委託がおすすめです。その理由としては、以下のような点が挙げられます。
まず、ホームページ制作会社は専門的な知識とスキルを持ったスタッフが在籍しており、最新のWEB技術やトレンドに精通しています。SEO、セキュリティ、ユーザビリティなど様々な観点から、専門的な提案と対応が可能です。自社で対応しようとすると、これらの知識を習得するための時間と労力が必要になり、効率的とは言えません。
また、制作会社は複数のクライアントサイトを運用するなかで得た豊富な経験とノウハウを持っています。「この施策は効果があった」「この方法は避けた方が良い」といった実績に基づいた判断ができるため、効果的なホームページ運用が期待できます。
さらに、ホームページ制作を依頼した会社に管理も委託するメリットは大きいです。サイトの構造や仕様を熟知しているため、スムーズな対応が可能ですし、制作段階からの一貫した戦略でホームページを育てていくことができます。別の会社に委託すると、引き継ぎの手間や認識のずれなどが生じる可能性があります。
費用対効果の面でも、専門家に委託することで、効率的な予算配分と効果的な施策の実施が見込めます。自社対応で生じる可能性のあるミスやトラブルによる機会損失を考えると、長期的には委託の方がコスト面でも有利な場合が多いでしょう。
ホームページが企業の重要な資産である以上、その管理も専門家に任せるという選択は、ビジネスの成長と成功につながる賢明な判断と言えます。
詳しくはこちらもあわせてご確認ください。
ホームページ制作は外注がおすすめ!メリットや制作の流れなどをわかりやすく解説
ホームページ管理を委託する業者を選ぶ際のポイント

ホームページ管理を外部に委託する場合、適切な業者選びが成功の鍵となります。単に価格だけで判断するのではなく、以下のようなポイントを総合的に考慮して、自社のニーズに最適な業者を選定することが重要です。信頼できるパートナーを見つけるための主なポイントを見ていきましょう。
実績が豊富かを確認する
ホームページ管理業者を選ぶ際、まず確認すべきは実績です。どのような企業のホームページを手がけてきたか、その管理実績は豊富かを確認しましょう。特に、自社と同じ業界や規模の企業のホームページ管理の実績があれば、業界特有の課題や要望に精通している可能性が高いです。
業者のポートフォリオや事例集を確認し、デザインの質やサイトの使いやすさをチェックすることも重要です。また、長期的にサイト管理を行った実績があるかどうかも重要なポイントです。短期的な制作だけでなく、継続的な運用・改善の実績があれば、より信頼性が高いと言えるでしょう。
可能であれば、実際に運用中のサイトを見せてもらい、更新頻度や内容の質、デザインの一貫性などを確認することも効果的です。実績豊富な業者は、様々な状況に対応できる柔軟性と問題解決能力を持っていることが多く、安心してホームページ管理を任せることができます。
Web上の口コミやレビューを確認する
業者の評判やサービスの質を知るためには、Web上の口コミやレビューが参考になります。Googleマップのビジネスレビューや、各種レビューサイト、SNSでの評判などをチェックしましょう。多くの顧客から高評価を得ている業者は、サービスの質が高い可能性が高いです。
特に注目すべきは、コミュニケーションの質やレスポンスの速さ、問題解決能力に関する評価です。ホームページ管理は継続的な関係性が重要なため、顧客との円滑なコミュニケーションができる業者を選ぶことが大切です。
また、否定的なレビューがある場合は、その内容と業者の対応も確認しましょう。問題が発生した際に、誠実かつ迅速に対応しているかどうかは、業者の姿勢を知る上で重要な情報です。口コミだけで判断するのではなく、業者に直接質問し、その返答の質や速さで判断材料を増やすこともおすすめします。
トラブル発生時に迅速に処置してもらえるかを確認する
ホームページ運用中には、予期せぬトラブルが発生することがあります。サーバーダウン、セキュリティ侵害、表示エラーなど、様々な問題に対して迅速かつ適切に対応してくれる業者を選ぶことが重要です。
サポート体制については、対応時間(平日のみか24時間365日対応か)、連絡方法(電話、メール、チャットなど)、平均対応時間などを事前に確認しておきましょう。特にビジネスクリティカルなサイトの場合は、緊急時の対応体制が整っているかどうかが重要なポイントとなります。
また、定期的なバックアップや監視体制の有無、トラブル発生時の対応フローなども確認しておくと良いでしょう。過去のトラブル対応事例を聞いてみるのも効果的です。問題発生時の対応力は、長期的なパートナーシップを築く上で非常に重要な要素です。信頼できるサポート体制を持つ業者を選ぶことで、安心してホームページ運用を任せることができます。
ホームページ制作を依頼した制作会社に相談する
ホームページを制作した会社に管理も依頼することは、多くのメリットがあります。制作会社はサイトの構造やシステムを熟知しているため、効率的かつ効果的な管理が期待できます。また、サイトのコンセプトや目的も理解しているため、一貫した方向性での運用が可能です。
制作会社に相談する際は、管理業務の範囲や更新頻度、費用体系について具体的に確認しましょう。また、将来的なリニューアルやシステム拡張についても、どの程度対応可能かを聞いておくと良いでしょう。
制作と管理を別の会社に依頼すると、引き継ぎの際に情報の欠落や認識のずれが生じる可能性があります。特に複雑なシステムやカスタマイズが施されたサイトの場合、制作会社でなければ適切に対応できないケースもあります。スムーズな運用を実現するためにも、まずは制作会社に管理の可能性を相談することをおすすめします。
マーカーネットはホームページの制作から管理まで対応可能!
ホームページ制作会社のマーカーネットでは、ホームページの制作から公開後の管理運用まで、一貫したサービスを提供しています。当社の強みは、クライアント企業のビジネス目標を深く理解し、それを実現するためのWEB戦略を提案・実行できる点にあります。
ホームページ制作においては、単なるデザイン制作にとどまらず、ユーザビリティの向上、コンバージョン率の最適化、SEO対策などを総合的に考慮した設計を行います。また、スマートフォンやタブレットなど様々なデバイスに対応するレスポンシブデザインを標準採用し、あらゆるユーザーに最適な閲覧環境を提供します。
公開後のホームページ管理においては、定期的なコンテンツ更新、セキュリティ対策、アクセス解析に基づく改善提案など、サイトの価値を継続的に高めるためのサポートを行っています。特に、アクセス解析とSEO対策には強みを持ち、検索エンジンからの流入増加と目標達成率の向上に貢献しています。
マーカーネットの管理サービスは、クライアントのニーズに合わせてカスタマイズ可能です。月に数回の更新だけを希望される企業様から、日々の更新と積極的なマーケティング支援を求める企業様まで、様々なプランをご用意しています。また、緊急時の対応体制も整えており、トラブル発生時にも迅速かつ適切に対応いたします。
ホームページは作って終わりではなく、育てていくものです。マーカーネットは、クライアント企業のビジネスの成長とともに、ホームページも成長させていくパートナーとして、長期的な関係構築を大切にしています。ホームページの制作から管理運用まで、ぜひマーカーネットにお任せください。
まとめ:ホームページの管理方法を理解しよう
ホームページの管理は、企業のオンラインプレゼンスを維持・向上させるために欠かせない業務です。本記事で解説したように、ホームページ管理には内容の更新、サーバー管理、SEO対策など様々な側面があり、それぞれに専門知識とノウハウが求められます。
管理方法の選択肢としては、自社で行う方法と外部委託する方法があります。自社に専門知識を持った人材がいる場合や、管理方法がマニュアル化されている場合は自社管理も可能ですが、専門知識がない場合や本業に専念したい場合は、外部委託を検討すべきでしょう。
費用面では、自社管理は人件費やツール費用などが発生し、外部委託は月額1万円〜10万円程度が一般的です。一見すると外部委託の方がコストが高く見えるかもしれませんが、専門知識や経験、効率性を考慮すると、長期的には外部委託の方がコストパフォーマンスが高い場合も多いです。
ホームページ管理の外部委託先を選ぶ際は、実績や口コミ、サポート体制などを総合的に判断することが重要です。特に、ホームページ制作を依頼した会社に管理も任せることで、一貫性のある効果的な運用が期待できます。
ホームページは企業の「顔」であり、24時間365日稼働している営業マンのような存在です。適切な管理によって、その価値を最大限に高め、ビジネスの成長に貢献させることができます。ホームページ管理の重要性を理解し、自社にとって最適な管理方法を選択しましょう。












